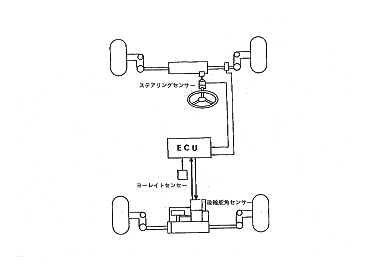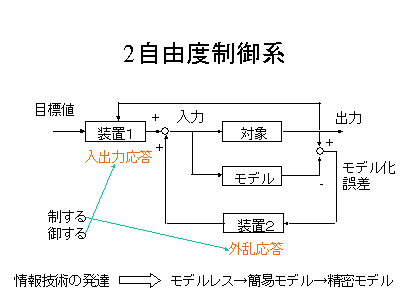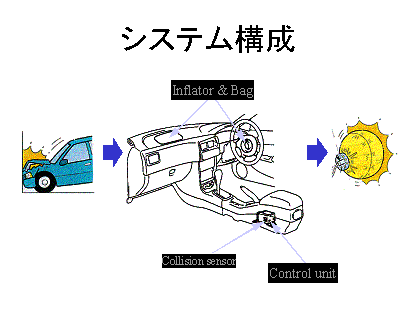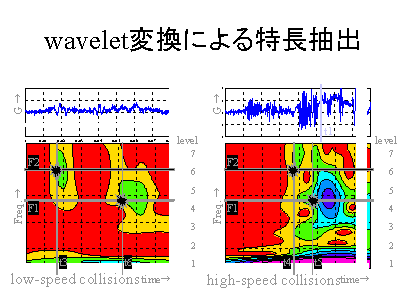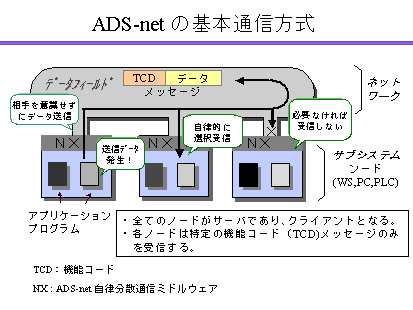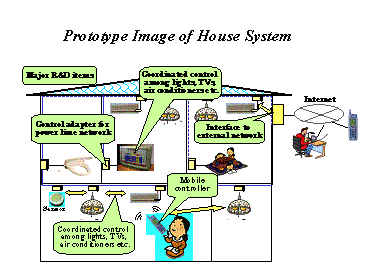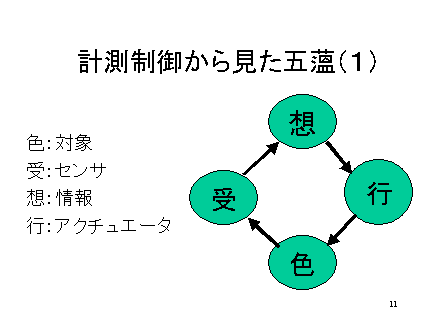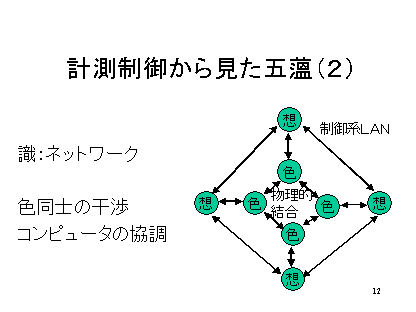|
研究紹介−計測制御と五薀
新 誠一 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻 shin@axis.t.u-tokyo.ac.jp 1.はじめに 私の専門は制御工学である.もっとも,「制御は全て」というポリシーで研究している.そのため,課題が与えられれば,それを制御の問題として解決することが私のパターンである.たとえば,鉄鋼,紙パルプ,セメント,自動車,家電,介護,IC,生産システム,ネットワーク,ソフトウェアとなどの制御応用を行ってきた.ジャンルは選ばないが,解決の道具は数学と物理とワンパターンである.もっとも,ジャンルごとに様相が違い,新たな課題が出てくる.つまり,制御応用を一つ終えると新しい理論が一つできるという感じである. 数学に基づく制御では,制御したい相手(対象)を数式で表現する.制御の目標も数式化する.これらの数式に基づいて,目的を達成する手法(制御装置)を設計するということが基本である.対象の数式化,目的の数式化に物理は必須である.また,装置として求められた数式を現実に動作させるためにも物理は不可欠である. このような数式に基づいた制御が可能となったのは,コンピュータのお陰である.コンピュータを動かすのにはソフトウェアが必要である.このソフトウェアを抽象化してアルゴリズムと呼ぶ.これは算法,つまり数式である.物もソフトも数式で書ければ,後は数学の世界.これが私のジャンルの広さを支えている.ただし,現実に使える方式でなければ工学として意味がない.腕の見せ所は,難しい問題を実現可能な形に落とし込む発想と技量である. 能書きはこのぐらいにして,どのような研究を行っているか,以下,実例に基づいて紹介していく.大きく分けて,制御工学,wavelet解析,自律分散システムの研究を行っている.この順番に簡単に紹介する.また,制御という言葉は一般的な概念であり,突き詰めると哲学の領域に入っていく.そのことを踏まえて制御から見た仏教の話,そして自律分散システムを発展させた創発システムの話をさせていただいて紹介の締めくくりとさせていただく.なお,突っ込み不足の点は,最後に上げた参考文献を参照していただければ幸いである.
2.制御工学 それでは,いくつか実例を紹介していこう.一つは,後輪操舵システムである(第1図).高速でのレーンチェンジをする場合に後輪が操舵することで安全に,かつ速やかに操舵するシステムである.横風の影響や,乗車人数,装着タイヤ,路面など変化が大きい要因の影響をできるだけ受けずにスムーズに動作することが望ましい.これに対し,第2図で紹介する2自由度構成の制御を利用した操舵システムを開発した.
第1図 後輪操舵システム.ハンドル角や車の回転速度情報に基づいてモータにより後輪を操舵する.トヨタアリストや富士重工のレガシーB4などに採用されている.
第2図 2自由度制御.対象が後輪操舵系,その数学モデルを並置することで,モデルとの誤差を検知し,それに応じて制御入力を変化させる.このことで横風や路面などの影響を受けないスムーズな車線変更が可能となる.
ここでは標準状態の数学モデルを実際の後輪操舵システムと並置させることで,モデルからのずれを検出し,そのずれに応じて制御の補正を行っている.これを2自由度構成と呼んでいる.このような制御が可能となったのは,マイコンの性能が著しく向上したためである.現在の自動車には,最新の携帯電話に使われているマイコンと同等のものが搭載されている.N504iと呼ばれる携帯電話に使われているNECのV850シリーズはトヨタ自動車に,P504iと呼ばれる携帯電話に使われている日立製作所のSHマイコンは日産自動車に搭載されている.これらのマイコンは初期のペンティアムを越える性能を持っており,1980年代に持て囃されたスーパーコンピュータであるクレイ・ワンの性能と遜色のないレベルである.ちなみに,ゲーム機PlayStation2が使用しているマイコンは,クレイ・ワンの30倍程度の性能を持っている. このようにマイコン性能が向上したため,鉄鋼や紙パ,セメントなどの大規模な施設でしか使えなかった数学モデルベースの制御が,自動車や家電,介護システムでも使えるようになってきた.そして,このことが私のアイデンティティの喪失と深く関係している.
3.wavelet解析 次にwavelet解析の実例を紹介しよう.これはフーリエ解析を精密化したものである.人にとって波は理解しやすい物理量である.音程と音色,そして強さで音を聞き分ける.才能のある人間は微妙な違いを聞き分けることができる.これの工学応用がフーリエ変換である.実は,このフーリエ変換は数学者のフーリエが微分方程式の解法の一つとして開発した数学理論であり,関数論という分野に属する.ヒルベルト空間とかバナッハ空間とか難しい世界の話であり,ほとんどの大学生が講義を聴いても全容を把握できない.それにも関わらず,フーリエ変換は実用の道具であり,音響やメカ系の技術者には必須である.よく大学の講義は実際の場で役にたたないと批判を頂戴するが,それは昔の話である.先に述べたようにマイコンが急速に発達しているため理論がそのまま実地に使える環境にある.それどころか,理論を活用して付加価値を高めることが今日の企業の大事な戦略である. 話を戻し,フーリエ変換を理論と応用の両面から見直したものがwavelet変換である.この技術を用いて,音声認識,画像処理,異常検出などを行った.その中の一つにエアーバッグの検出装置がある(第3図).ご承知のとおり,エアーバッグは衝突時に開いて乗員を保護する安全装置である.しかし,むやみに開かれても困る.開けば運転出来なくなるし,眼鏡の破損,心臓麻痺などが起きる可能性がある.しかも,衝突形態は正面衝突,オフセット衝突,側突,トラック荷台への潜り込み,電柱など種々の形態がある.実は,速度とぶつかり形態に応じてエアーバッグを開くべきか否かが決まっている.それを満たすように,開閉装置を設計することが技術者の仕事である.もっとも,判断は数十ミリ秒で行う必要がある.つまり,1秒の数十分の1の時間で開閉を判定する必要がある.
第3図 エアーバッグシステム.衝突を加速度変化で検出する.その信号を処理してエアーバッグを開くか開かないかを瞬間に判断する.
第4図 衝突信号とそのwavelet変換結果.時間−周波数面で特徴的なパターンを見つけ,そのパターンに対応したデジタルフィルターを作成する.
ここでは,加速度信号をwavelet変換した第4図に基づき,開閉ロジックの大本となるデジタルフィルターを作成した.このフィルターも数式で記述される.
4.自律分散システム 次に自律分散システムを紹介しよう.ネットワーク技術の時代であるが,基本は情報共有である.そして,情報共有には放送が有効なことはテレビやラジオのニュースを視聴している人なら良く知っている.しかしながら,情報系では通信が中心である.これは,一人一人に電話をかける世界であり,共有には効率が悪いとともに,相手によって内容を変えれるという透明性の問題がある.そこで,放送を主体とする情報共有システムを日立製作所が開発し,首都圏のJR電車や新幹線の運行管理や新聞の印刷,ビールの製造などに使っている(第5図).時代がオープンへと向かっているとういう認識で,これを世界の規格にすることになった.それは(財)製造技術センターが受け皿となったFAオープン推進協議会で標準化を進めることとなった.この結果,ISO15745の最終投票を待っている段階である. なお,同様の仕組みは,家庭ネットワークにも導入している(第6図).このネットワークの動作の最適化を数理的に解析している.
第5図 放送型情報共有の原理.情報は放送され,各サブシステムが取捨を選択する.ISO15745として標準化が進められている.
第6図 放送型によるメーカーや機種を超えた情報共有
5.五薀と計測制御 以上のように数学をベースとする産業応用を行っている.研究・開発していることは最先端との自負があるが,実はお釈迦様の手を出てはいない.以下,これまでの研究内容の枠組みから仏様の教えを見直してみよう. この紹介のように自分の知識を開陳することを「薀蓄を垂れる」という.この薀は仏教用語である.広辞苑第5版によれば,
五薀 (仏)( 薀は梵語 skandha 集合体の意) 現象界の存在の五種の原理.色(しき),受(じゅ),想(そう),行(ぎょう),識(しき)の総称で,物質と精神の諸要素を収める.色は物質および肉体,受は感受作用,想は表象作用,行は意思・記憶など,識は認識作用・意識.一切存在は五薀から成り立っており,それ故,無常,無我であると説かれる.
とある.何だか分からないが物質と精神の世界は五薀に帰着できるようである.これを専門とする計測制御から見たものが,第7図,第8図である.「色」として対象があり,その状態を「受」,センサが測定し,それに基づいて「想」であるコンピュータが演算する.その演算結果を「行」に対応するアクチュエータ,つまり,モータや油圧装置が対象に働きかける.これが計測制御の世界である.第8図に示すように「識」はネットワークである.
第7図 色,受,想,行は電子制御の世界
第8図 識はネットワーク
お釈迦様は世の中に,この五つしかないとおっしゃっている.それなら,私の主張である「制御は全て」はお釈迦様が裏打ちしてくれるということになる.そして,世の中全体に向かい合っているためにアイデンティティの喪失が起こる事がわかる.
7.まとめ 最後に,「識」にかけて創発システムを紹介する.五薀の話で述べた「識」は繋がりであることを容認頂くと,知識は知の繋がりである.学識は学の繋がりである.見識は繋がりが見えるということである.インテリジェンスはつながりである.人と人,物と物,事と事,そして人と物と事を結びつけることで新たな世界が広がる.これが創発であり,これを数理的に扱っているものが創発システム論である.もっとも,数理的以前に分かることがある.それは,つながるためには複数の手を持たねばならいないということである.手が一つしかなければ,王子様とお姫様は目出度くゴールインとなり,話は終わり.話が広がるためには,王子様が別な姫に手を出せば失楽園が始まり,王子様が母親に縛られていれば嫁姑戦争が始まる.良し悪しは別にして,新しい展開は一つの物や事,そして人に複数の理解があるか否かで決まる.つながりが人の命,一つからの脱出を餞に本紹介を終えることにする.
参考文献 1)新,ハロー!PHS −マンガとイラストで語るマルチメディア革命,オーム社(1995) 2)新,制御理論の基礎,昭晃堂(1996) 3)新,たまごっち学術孝 ―イラストで語る商品創発,オーム社(1997) 4)新,無責任体制の終焉 ―さらば文系,さらば理系−,名著出版(1997) 5)木村,美多,新,葛谷,制御系設計理論とCADツール,コロナ社,1998 6)新,田原,福田,他,ヘルスモニタリング(山本鎮男編),共立出版,1999 7)新他,ゲーム−駆け引きの世界−,東京大学出版会 (1999) 8)新他,知の創発(伊藤宏司編著),NTT出版,2000 9)新他,「難しい問題を解きほぐす複雑工学」,工学は何をめざすのか(中島尚正編),東京大学出版会,2000 |